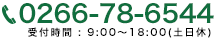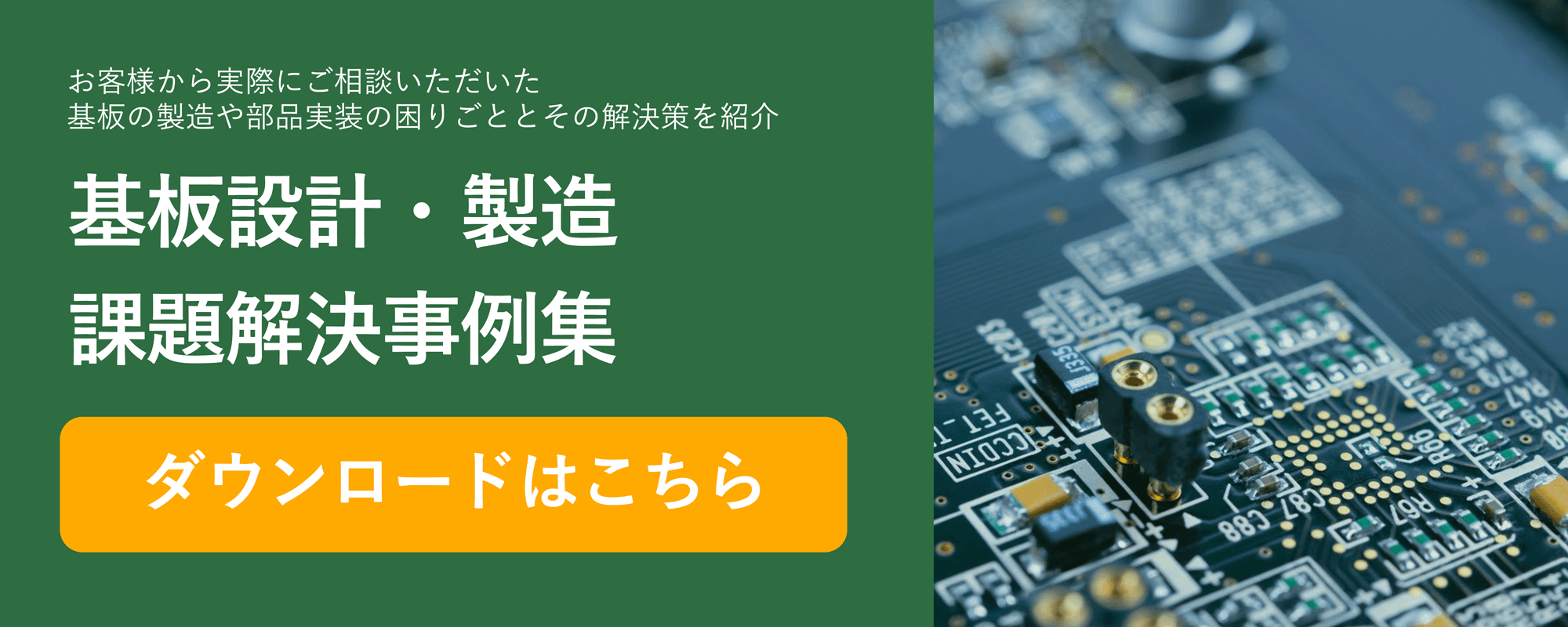電子機器の高性能化と小型化が進む中、設計者にとって避けて通れないのが“熱対策”です。
特に、回路基板(プリント基板、PCB)は、ICや電源モジュールなど多数の発熱部品を搭載するため、熱が集中しやすく、そのままでは製品の故障や性能劣化を引き起こすリスクがあります。
かつてはヒートシンクやファンによる空冷が主流でしたが、近年では基板そのものを放熱経路として活用する設計も多くなってきています。
実際、BGAやQFNなどの小型部品では、発生した熱の90%以上が基板を通じて逃げているとも言われています。
つまり、放熱性能は部品の能力や筐体設計だけではなく、「基板設計」の段階で大きく左右されるということです。
本記事では、放熱性を高めるための基板設計の基本原則から、材料選定、レイアウトの工夫、実装時の注意点までを網羅的に解説します。これから放熱を意識した基板設計に取り組む方にとって、実践的なガイドとなることを目指しています。
1. 放熱設計の基本原則
1-1. 熱の移動メカニズム
- 伝導(Conduction)
熱が物質内部を移動する現象です。たとえば、ICチップからリードやパッドを経由して、基板上の銅パターンや内層に熱が伝わっていきます。PCBではこの伝導が最も主要な放熱経路です。 - 対流(Convection)
空気や液体などの流体の動きによって熱が運ばれる現象です。ファンによる強制空冷や、自然空冷などがこれに該当します。基板の表面から外気への熱移動に関わります。 - 放射(Radiation)
赤外線などの電磁波として熱が放出される現象です。電子機器の温度帯では微小ですが、筐体設計によっては効果が現れることもあります。
基板設計では、これら3つの中でも「伝導によって基板内に熱を逃がし、外部へと分散させる」ことが最も重要となります。
1-2. 基板設計が放熱のカギを握る理由
ICなどの表面実装部品、とくにBGAやQFNといったパッケージでは、熱がパッケージの底面から基板に伝わる構造になっています。
そのため、熱の大部分は空気中へ放出されるのではなく、基板内の銅箔やビア、内層を通って拡散されていくことになります。
つまり、同じ部品を使用していても、「どのような基板構成で」「どのようにパターンを引き」「どれだけ放熱経路を確保できるか」で、最終的な温度や寿命は大きく変わってきます。
1-3. 熱を逃がす=熱を受け止める経路を設計する
放熱設計とは、単に“冷やす”方法を考えるのではなく、熱をどこからどこへ、どのように流すかを設計することを指します。
- 熱が発生する部品はどこか?
- その熱はどの経路で基板に伝わり、どこへ逃がすか?
- 逃がした先に熱が滞留しないか?
これらを考慮して初めて、基板の放熱設計が成り立ちます。
2. 基板材料と構造の選定
放熱性の高い基板を設計するうえで、最初に考慮すべきなのが「材料」と「構造」の選定です。回路の設計や部品の配置がいくら適切でも、熱を受け止める基板自体に放熱性がなければ、効果的な熱拡散は望めません。
ここでは、放熱性向上に寄与する基板材料と、熱を効率的に分散させる構造の設計ポイントを紹介します。
2.1 放熱性を高めるための基板材料
標準FR-4基板
一般的な電子機器で多く使われている「FR-4」材料は、コストや加工性に優れていますが、熱伝導性はそれほど高くありません(熱伝導率:0.3〜0.5W/m・K程度)。
そのため高放熱を求める場合は、下記のような特殊材料を検討する必要があります。
アルミベース基板(メタルコアPCB)
アルミベース基板は、絶縁層の下にアルミニウム製の金属コアを設けた構造で、高い熱伝導率を持ち、LED照明やパワーエレクトロニクスなどの用途に最適です。
ただし、放熱性に優れる一方で、多層構造の対応が難しく、加工にも一定の制約があるため、用途に応じた慎重な選定が求められます。
銅インレイ基板
銅インレイ基板は、高熱伝導性を持つ銅材を基板内部に埋め込む構造で、局所的な発熱に対して効率的に熱を吸収・拡散できるのが特徴です。
設計の自由度が高く、高密度実装にも柔軟に対応できるため、熱対策が求められる多様な用途に適しています。
参考:課題解決事例「金属製の放熱基板を採用し、LED基板の放熱性と熱伝導率を向上」
セラミック基板(AlN、Al₂O₃)
セラミック基板は、最大200W/m・K以上という非常に高い熱伝導性と優れた絶縁性を兼ね備えており、車載機器や高周波回路など高い信頼性が求められる製品に適しています。
一方で、成形や加工が難しく、製造コストが高くなりやすい点には注意が必要です。
2.2 多層基板と熱プレーンの活用
基板の放熱設計では、銅箔層の配置によって熱の拡散性能を向上させることが可能です。
特に多層基板では、内層を活用した放熱経路が放熱に有効です。
熱プレーン(GND/POWER層)の活用
熱源となる部品の真下には、広い面積を持つGND層や電源層(パワープレーン)を配置することで、熱を基板全体に面で効率よく拡散させることが可能です。
特に裏面放熱型のパッケージでは、中央パッドから内層へと熱が流れる構造が前提となっているため、こうした銅箔面積の確保は放熱設計において非常に重要なポイントとなります。
ビアによる多層連結
複数の層にわたって熱を効率的に移動させるには、スルーホールビアの活用が有効です。
特に熱源パッドには多数のビアを設け、GND層や外部の放熱構造へと熱を伝える設計が推奨されます。
さらに、銅めっきされたビアや充填ビア(フィルドビア)を使用することで、熱伝導性を一層高めることができます。
2.3 材質・構造選定時の注意点
基板材料を選定する際は、放熱性能だけでなく、コスト、加工のしやすさ、実装の難易度といったバランスも重要です。たとえば、アルミ基板は高い放熱性を持つ一方で、多層構造や高密度実装には不向きという制約があります。
また、銅インレイ基板やセラミック基板は優れた性能を発揮しますが、製造コストの上昇や納期の長期化といった影響も考慮する必要があります。
放熱性を高めるには、「単に分厚い銅を使えばよい」というわけではありません。用途や発熱量に応じて、適切な材料と構造を組み合わせることが最も効果的な放熱設計につながります。
3. レイアウト設計のポイント
放熱性の高い材料や構造を採用しても、それを十分に活かせるかどうかは「レイアウト設計」にかかっています。
電子部品の配置、パターンの引き方、銅箔の使い方など、細部の設計次第で熱の拡散効率や温度分布に大きな差が生じます。
ここでは、放熱性を最大限に高めるためのレイアウト設計上の重要ポイントを、実践的な視点から解説します。
3-1. 熱源部品の配置と配置戦略
基板上の発熱源であるCPUや電源IC、MOSFETなどは、できる限り放熱効率の良い場所に配置することが求められます。
中心部よりも空気の流れや筐体の放熱構造に近い外周部に配置することで、熱が基板内に滞留せず、外部へ効率よく逃げるようになります。
また、複数の発熱部品が密集しないように分散させることで、局所的な温度上昇を防ぎ、基板全体の温度を均一に保つことができます。加えて、熱に弱い部品(光センサや電解コンデンサなど)との距離を確保することも重要です。
3-2. 銅箔の厚みとパターン設計による熱拡散
熱は主に銅パターンを伝って基板内に広がるため、銅箔の厚みとパターン設計も放熱性能に大きく影響します。標準的な35μm厚の銅箔よりも、70μmや105μmといった厚銅仕様を採用することで、より多くの熱を効率的に拡散できます。
また、熱源となるパッドとGNDプレーンを、できるだけ短く、太いパターンで接続することにより、熱の流れを妨げないスムーズな拡散経路が形成されます。
さらに、銅箔面積を広く確保することで、基板全体に熱が均等に広がる設計が可能になります。これは放熱だけでなく、電気的なインピーダンスや電流容量の点でも有利に働きます。
3-3. ビアの配置と多層接続による縦方向の熱拡散
基板内部のプレーンと熱源をつなぐ役割を果たすのが「ビア」です。
とくにQFNやLGAなどの裏面放熱型パッケージでは、中央の放熱パッドから複数のビアを通じて、内層や裏面へと熱を導く構造が基本となります。
ビアはパッドの中央から密に配置することで、熱を効率よく多層に伝導させることができます。さらに、銅めっきされたスルーホールビアや、内部に銅を充填したフィルドビア、あるいはスタックドビアを使うことで、より高い熱伝導性能を実現できます。
実装時のはんだ吸い込みなどにも配慮し、ビアの開口処理や封止方法を検討することも重要です。
3-4. 放熱パッドと部品接続の最適化
放熱性を高めるためには、部品パッケージの放熱パッド(exposed pad)とGND面との密接な接続が不可欠です。
放熱パッドから下層の銅箔へ熱を伝え、その後ビアやプレーンを通じて熱を広く拡散させる設計が基本となります。
特に、リフロー実装時にはクリームはんだの適正な印刷量を確保し、部品の浮きや接触不良が発生しないようにする必要があります。これにより、電気的な接続と同時に、熱的な安定性も確保されます。
3-5. 放熱阻害要因への対処と全体設計の最適化
銅箔パターンのスリットや配線密度が高すぎる設計、不要なビアの配置は、せっかくの熱伝導経路を遮断する原因になります。
信号線との干渉がある場合は、層を分けて配線することで熱経路を確保する工夫も必要です。
また、部品の向きや配置によってはリフロー時の加熱均一性や自然対流の効果にも差が出るため、実装性と放熱性の両面から全体設計を見直すことが大切です。
このように、レイアウト設計は熱設計における“仕上げ”とも言える重要なプロセスです。
材料や構造が整っていても、レイアウトで誤ると放熱性能は大きく損なわれます。部品配置からパターン、ビアの設計に至るまで、細部にわたって放熱を意識した設計を徹底することが、長寿命で安定した電子機器を実現するカギとなります。
4. 部品実装・製造時の注意点
放熱性を意識した基板設計は、回路設計やレイアウト段階で完結するものではありません。部品実装や製造の現場で設計意図を正しく再現できなければ、期待した放熱性能は得られず、かえって不良や故障リスクを高めてしまう可能性もあります。
本章では、設計内容を確実に形にするために、実装・製造工程で特に注意すべきポイントを解説します。
4-1. 放熱パッドへのはんだ印刷と実装精度
裏面放熱型パッケージの中央パッドは、電気的な接続と同時に、熱伝導の重要な経路となります。そのため、メタルマスクによるはんだ印刷の最適化が不可欠です。
クリームはんだの量が多すぎれば部品が浮いて接触不良の原因になり、逆に少なすぎれば十分な熱伝導が得られません。
中央パッド部分には開口面積を分割したメタルマスクパターン(たとえば3分割や5分割)を採用することで、はんだ溜まりやボイドの発生を抑え、安定した接続が可能になります。
4-2. 熱に弱い/熱容量の大きい部品への対応
実装する部品の種類によっても、熱に対する配慮が必要です。
たとえば、プラスチックモールド部品や光学センサなどは熱に弱く、はんだごてやリフロー加熱の温度プロファイルを最適化しなければ変形や性能低下を引き起こす恐れがあります。
一方で、大型のコイルやアルミ電解コンデンサなどは熱容量が大きいため、はんだごてでは十分な加熱が難しく、はんだがうまく溶けないといったトラブルも起こり得ます。
その場合は、基板全体をあらかじめ温める「プリヒート処理」や、はんだ槽の温度調整などによって補完する必要があります。
4-3. 高放熱基板の取り扱いと加工精度
放熱を重視した基板では、アルミベース基板や厚銅基板、銅インレイ基板といった特殊構造が採用されることもあります。これらの基板は熱伝導性に優れる一方で、機械加工や実装条件に制約がある点にも注意が必要です。
たとえば、アルミ基板はドリル加工に特殊な刃物が必要となり、リード部品の挿入に制限が出る場合があります。また、厚銅基板ではパターン間の絶縁距離が確保しづらく、電気的な安全性に影響を及ぼすこともあります。
設計段階でこれらの特性を理解し、実装業者や基板メーカーとの十分な連携・事前確認を行うことが、トラブルを未然に防ぐカギとなります。
4-4. 実装前提でのビア構造・パターン処理
ビアを配置する際には、実装時の「はんだ吸い込み」への対策も必要です。特に、中央パッドに開いたビアからは、リフロー時にクリームはんだが穴に吸い込まれてしまい、接合不良の原因となることがあります。
これを防ぐためには、ビア穴径を小さく設定したりフィルドビア(穴を充填)などの処理を事前に指示しておくことが重要です。こうした細部の実装性も含めて考慮することで、設計と製造の“ズレ”を最小限に抑えることができます。
熱対策は、単に部品の発熱量を減らしたり、冷却ファンを追加したりするだけではなく、「設計→製造→実装」まで一貫して整合性の取れた対応が求められます。放熱を意識した設計が製造現場で正しく再現され、かつ量産に適した安定性を備えているかどうかを意識することが、放熱設計の成功につながります。
5. まとめ
基板の放熱設計は、部品配置やパターン設計といったレイアウト面だけでなく、材料の選定や製造時の配慮も含めた包括的な取り組みが求められます。
製品に発生する熱の90%以上を基板経由で逃がすことができるとされており、基板の放熱性能=製品信頼性といっても過言ではありません。 「材料」「構造」「パターン」「製造条件」これらすべてを最適化することが、放熱設計成功のカギとなります。
6. 基板の放熱性でお困りの際はAPNにご相談ください
私たちはファブレスメーカーとして、基板設計〜製造・実装まで多様な案件に対応しています。
過去にも「金属製の放熱基板を採用し、LED基板の放熱性と熱伝導率を向上」など、基板の放熱性に関するお客様のご相談も多数解決してきました。
製品の用途や予算などを考慮し、QCDのバランスが取れた放熱性改善のご提案が可能です。
プリント基板の熱対策でお困りの際はお気軽に当社までお問い合わせださい。